シリコンバレーの企業とコラボレーションした多彩な実習
最近、地の利を生かしてシリコンバレーの企業とコラボレーションした実習を行っています。この実習では、学部を越えたチーム編成で企業から出される課題に取り組んでいます。
アカデミー・オブ・アートにはウェブニューメディアという学部があり、そこには「ユーザーインターフェイス(UI)」のクラスがあります。
この学生と工業デザイン学部の学生、また、必要に応じてファッション科のテキスタイルデザインの学生も集め、総勢20人くらいの学生を3~4人ずつのチームに分けるんです。例えばインテリアデザインの場合、2次元のグラフィックやAliasで作った3次元デザインまでは従来の講義でも行っていたんですが、ここにニューメディアの学生が加わると、コーディングができるようになり、実際に動くプロダクトが作れるんですよ。これにVRやARが加わると、実物大のものに触る疑似体験までできるようになります。
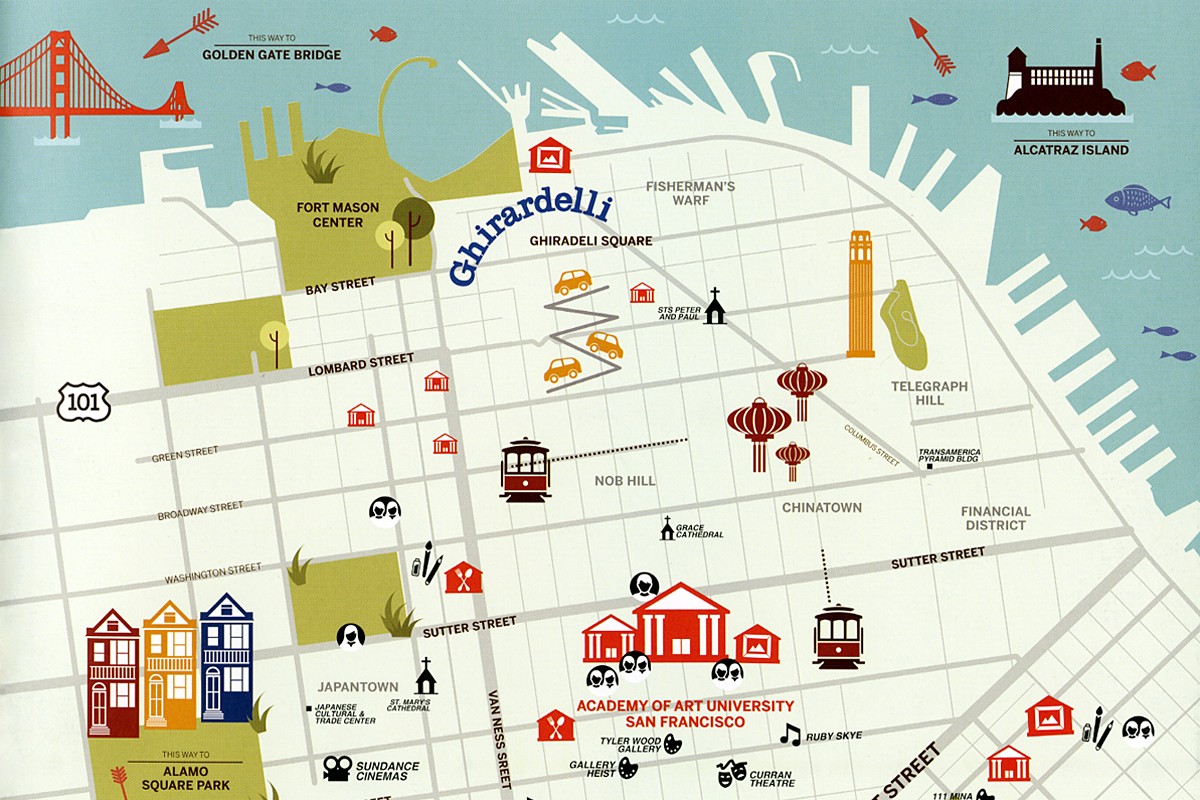
他にも、工業デザイン学部は他学部の学生とのコラボレーションをかなり積極的に行っています。
2次元を専門に学んでいるグラフィックデザイン学部との合同クラスでは、シャンプーボトルのパッケージデザインなどを開発するプロジェクトが動いています。
また、映画制作学部の音楽科とコラボすることもあります。箱を工業デザイン学部の学生が作り、BGMを音楽科の学生が作るんです。ビールが入った箱を開けたら炭酸の泡立つ音がするとか、ゴルフのパターが入った箱を開けたら打球音がするとか……とても面白いですよ。

チームプレイを学ぶ場となったり、多くの刺激と気づきの機会になるということはもちろんですが、工業デザイナーとしてプロを目指すのであれば「工業製品のデザインだけ」を考えていたのではスキル不足になると考えているからです。
最近、自動車業界では、カーシェアやUberといった新しいサービスが登場しています。自動運転技術も今後、開発が加速化していくでしょう。そうした中、カーデザインも変化の時代を迎えています。例えば、無人運転のトラックが現実のものとなれば運転席がいらなくなりますし、そうなると、キャブデザインの方法も変わります。そもそもあんな大きなキャブは必要なくなるでしょう。
これまでにないサービスや技術が開発されれば、インフラを巻き込んだデザインを行う時代が来るでしょう。荷物の積み卸しが無人化されたり、小型の荷物はドローンで配達されるようになったりと、流通機構の仕組みが変化することを踏まえたうえでカーデザインを行う必要が生じるのです。
仮に無人でトラックが走るようになったら、モーテルやロードサイドレストランなども必要なくなる一方、コマンドセンターが必要になってくる。
都市計画とまでは言いませんが、人・建築・カーデザインを一緒に考えればもっと面白いものができるだろうし、そういうことを学生のうちの他の学部とのコラボレーションで体験してもらいたいと思っています。
そうですね、色々と工夫してきましたが、例を一つ挙げるなら、トランスポーテーションの学科に「インテリアだけを学ぶクラス」を創りました。このクラスは1学期の全期間を通して開講されます。
これまで、エクステリア・デザインのクラスでインテリアを学ぶことはあっても、インテリアだけを1学期を通じて学ぶということは前例がありませんでした。このアイディアは、マツダに勤めていた頃にインテリアのポートフォリオが少なくて悩んだ体験から生まれたものです。
車が好きでカーデザイナーになりたいという学生は、車の外観をデザインしたいのですから、インテリアデザインなど最初は興味を持ちません。しかし実際にインテリアを学んでみると意外に向いていたり、インテリアのほうが面白いと感じたりする学生が数名出てくるんです。そうした学生は、先ほどのクレイモデラーの例と同じく、シニアレベルのクラス課題をインテリア専門に振り分けることが出来ます。
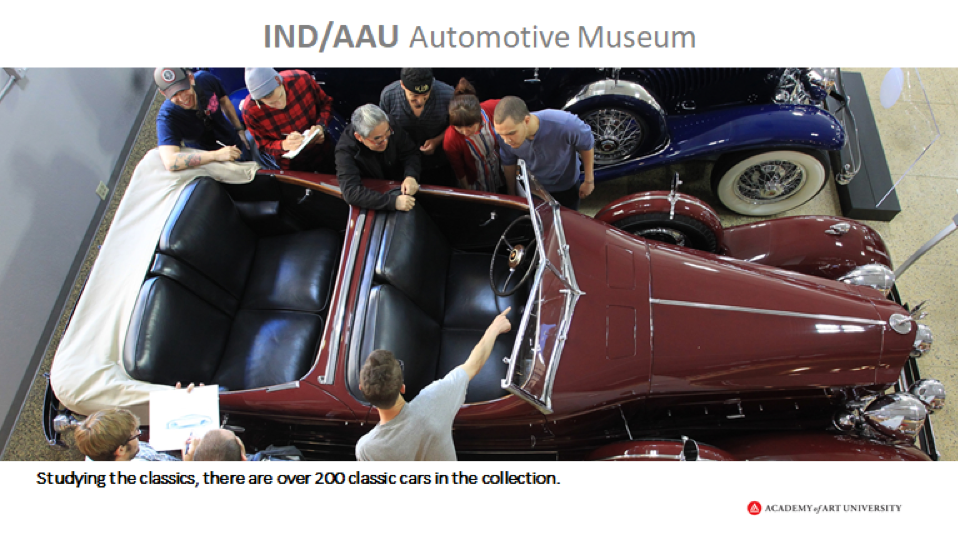
学校全体の割合で言えば33パーセント、工業デザイン学科に関して言えば42~43パーセントがアジア系の学生です。国籍は、中国本土、台湾や香港などの中国系がほとんどで、タイやインドネシア、インドの学生も増えてきました。
日本人はアニメやゲーム、ファッションなどを専攻する学部にはいるんですが、工業デザイン学部にはここ数年、在籍していません。過去にいた日本人学生は、皆途中でつぶれてしまいました。残念でなりません。
時代によって学生のタイプが変わっていくのは自然なことです。卒業間際の学生が、新入生を見てびっくりしているくらいですから、僕らが今の学生を見てどう思うかなんて推して知るべしですよ。
少し厳しいことを言うならば、最近の学生は、インターネットからあらゆる情報がもたらされる時代に育ってきたために自分たちから答えを探しにいこうとしない傾向にあると思います。自分で探さなくても答えがもらえると思っているんです。
また、絵のクラスではきちんと描けるけれども、デザインのクラスに移った途端に描けなくなる、という学生も多いですね。どうして描けないのか尋ねると、絵のクラスでは絵の評価だけで成績がつけられ、デザインのクラスではデザインの評価だけで成績がつけられる、だから絵とデザインは全く別物だと考えているんです。
そうではなく、絵のクラスで学んだことをデザインのクラスで活用し、さらにレベルアップするよう教えるんですが、なかなか理解してもらえない。ドローイングがワン、ツー、スリーとステップアップするのに併せてデザインの技量も向上してくるものなんですが、そこがつながらない。アメリカの小学校では近年、美術の授業数が減らされているようですから、もしかするとその辺りの基礎から始めなければならないのかもしれません。
授業数といえば思い出すことがあります。僕らの時代には工業デザインとトランスポーテーションの2学部を専攻することができたのに、今の学生はそれができない。なぜなら、僕らの時代にはなかったコンピュータのクラスが必修になっているからです。手描きの絵も学びながら、コンピュータも履修しなければならないので、他のクラスを学ぶ余裕がなくなっていることは、問題だと感じています。

最近の若いデザイナーは自分の手で車を洗車し、練りワックスで磨いた経験がないのかもしれませんね。ワックスを使ったことがあったら、絶対にしないようなデザインをよく見かけると感じています。最近は保険会社の方針が変わり、事故修理の際には板金修理をせずにパネル交換で済ませるようになりました。デザイン画通りにスタンピング(圧縮成形)板金がいかようにもできるようになり、これまでは歩留まりなり板金修理容易性なりと様々な制約があったものが、大きく変わってきています。
同時にデザイン・ツールも変化しており、ツールに引っ張られたデザインだと感じるものも多くあります。コンピュータ上でデザインしたものをくるくると回せばハイライトがピカピカと光るので、やっていて楽しいだろうと思います。でも、骨格のないまま化粧だけ施した車のデザインは長持ちしません。骨格の部分までしっかりと作り込んでこそ、お化粧も映える。これを伝えたいですね。
本気でデザインを極めたいなら「自分のものさし」を持つこと。この感覚を忘れないで欲しいと思います。少し前の「面がいい」と評価されている車を、洗車したりワックスがけしたりして五感を研ぎ澄ませてから、今取り組んでいるデザインに臨んでもらいたいと思います。




