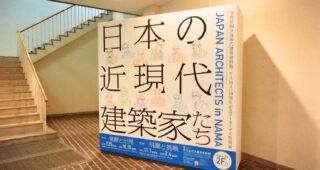月の開発を本気で目指す宇宙ベンチャー、ispace
空飛ぶクルマの次は、宇宙だ。ispaceは、史上初の民間月面探査を目指すスタートアップ。「本気で月を目指してるの!?」とびっくりしてしまったが、プロジェクト(HAKUTO-Rと呼ばれている)の内容を聞いてみると、着実に歩みを進めていた。イーロン・マスク率いるSpace Xのロケットを使用し、2021年に月面着陸、2023年に月面探査を実現する計画だ。
現在「着陸船」と「月面探査ローバー」を開発しており、写真は後者のモックアップ。従来のローバーと比べて小型・軽量なのが特徴だ。同社グローバル・コミュニケーション・スペシャリストのアーロン・ソレンソン氏がスマートフォンのアプリから遠隔操作で動かすデモを見せてくれた。


宇宙開発には、巨額の資金が必要だ。実は同社は2017年、シリーズAとして100億円以上の資金調達に成功しており、日本、アメリカ、ヨーロッパのルクセンブルグに100名以上の社員がいる。ispaceはこの分野のベンチャーとしては、最も調達額が大きく、規模も大きい会社なのだ。
さらに国内の大企業がそれぞれの強みを生かしてパートナーとして参加している。例えば日本航空は、成田空港の施設の一部をiSpaceの開発拠点として提供し、三井住友海上は、新たなリスクに対する保険などを研究している。シチズンはステンレスの5倍以上の強さを持つ独自素材「スーパーチタニウム」を提供。スズキは着陸船の強度計算などを支援。スパークプラグで有名な日本特殊陶業(NGK)は月面探査用の全固体電池を開発しているという。
将来的には月で水などの資源探査・開発を行い、月面開発のためのプラットフォームを目指すというispace。2年後の月着陸が楽しみだ。
ブロックチェーンでEVのインフラを支えるINDETAIL
札幌に拠点を置くINDETAILが展示したのは、EV時代に向けた技術。ブロックチェーン技術を使ったEVスタンドのプラットフォームだ。北海道電力との共同研究として進めており、現在はシステム設計の真っ最中。2020年度には実証実験を始めるという。

EVは災害時の非常用電源としての性格も持ち、そこに電気を供給するEVスタンドは重要な社会インフラとなる。ブロックチェーンを採用したのは、そのインフラを支えるセキュリティや冗長性、拡張の容易さなどを備えているから、とエンジニアのオレグ・パンコフ氏が解説してくれた。

将来的にはユーザーが自宅のソーラーパネルで発電した電気を仮想通貨のコインに変え、そのコインを電気代に充てたりEVを充電するために使えるようなしくみを想定しているそうだ。こういったブロックチェーンによる価値流通の仕組みは東京電力、中部電力、東京ガスをはじめとした電力・ガス各社がそれぞれ取り組んでいる分野。INDETAILでは北海道電力との研究で得た技術をドイツに展開する目的でIFAに出展したという。
折しもIFAの会期中、台風15号が千葉県の大規模停電を招いた。こういった災害にもブロックチェーンは比較的強いのが特徴。特定のエリア内で電気をやりとりするマイクログリッドと組み合わせることで、例えばどこかの送電網が切れた場合でも、地域内で電気の自給自足ができる。今後ますます必要とされる技術になりそうだ。
ハンズオフ走行を支える高精度地図、ダイナミックマップ基盤
2019年秋、日産のスカイラインに搭載されたプロパイロット2.0が、ついに高速道路での手放し走行を実現した。なぜ日産が国内メーカーの先陣を切って実現できたのか。その背後にある技術が、HDマップ(高精度3次元地図)だ。
ダイナミックマップ基盤は、そのHDマップを作っている会社。日本全国の高速道路、自動車専用道路をセンチメートル級という非常に高い精度でデータ化している。GPSと組み合わせることで、自分がどの道路の、どの車線を走行しているのかがセンチメートル単位で分かるのだ。標識の位置や立体交差の形状なども、正確に再現されている。このHDマップを活用して、地図から導き出した走行ラインを正確になぞることでハンズオフ走行が実現できるのだ。

同社は2019年6月に米国で同様の地図を手がけるUshrを買収。ちなみにUshrの地図はキャデラックが搭載する世界初のハンズオフ走行システム「スーパークルーズ」に使われている。
さて、そんなダイナミックマップ基盤がIFAに出展したのは、ハンズオフ走行や自動運転をアピールするためではない。HDマップという高精度な3次元データは、自動車メーカー以外にもさまざまな使い道があるはず、と同社は見ている。
例えばドローンの運行管理。HDマップは建物の形状まで3次元データで再現できる。マンションの501号室のベランダに荷物を届ける、などというときにはHDマップが必要になるだろう。あるいは、除雪車を走らせるときにも役立つ。雪が積もると路面が見えなくなってもHDマップがあれば自分が車線内にいるかどうかが分かる。そのほかにも道路のメンテナンス、インフラ施設管理、防災シミュレーションなど、多くの用途が考えられる。
自動車関係者が集まる大規模な展示会といえばIAA(ドイツ・フランクフルトモーターショー)が知られており、IFAの翌週に開催される。しかし、前述したようなHDマップの新たな可能性を開拓するため、より幅広いビジネスパーソンが集まるIFAに出展したそうだ。
日本発のスタートアップがたくさん集まった2019年のIFA。空飛ぶクルマ、月面開発など、「いつかそういう時代が来るかもね」くらいに思っていたことを本業とする会社があり、しかも具体的な計画を持って力強く進んでいる姿に驚かされた。現在、自動車業界は100年に1度の大変革などと言われ、電動モビリティや自動運転に注目が集まっているが、さらにその先、空や宇宙のモビリティも動き始めているのだ。これから、ますます乗り物が面白くなるな、とうれしくなった取材だった。