リニューアル記念展「百年の編み手たち──流動する日本の近現代美術」
そうした「地域志向」は、リニューアル記念展の中でもはっきりと示されていた。
「百年の編み手たち──流動する日本の近現代美術」と題された企画展で、展示室の冒頭を飾る作品が、1882年生まれの画家・石井柏亭(いしい・はくてい)による、その名も《木場》(1914年)と題された木版画だったのだ。
そこには、1914年の木場の風景が鮮明に写し取られている。資材として使われるであろう木材が水面にどこまでも浮かんでいる様からは、80年後のこの地域に日本最大級の現代美術館が建てられることになるとは誰にも想像できなかったはずだ。
そうした「地域志向」の作品から幕が上げられた「百年の編み手たち」展は、1910年代から2010年代に至るまでの100年間の日本の美術を「編集」という視点から捉え直そうとするものだった。
展覧会の冒頭には次のような解説が付されている。
情報化の進んだ現在では、様々な要素を選択的に編集する態度や、ハイブリッドな文化のありかたは、世界共通のものとなっていますが、近代以降の日本の美術は、そのようなありようを先駆的に経験し、編集自体を、作品の主題として、独自の制作を進めてきた作家の存在によって特徴づけられます。
たとえば、岸田劉生(きしだ・りゅうせい)による有名な《椿君に贈る自画像》(1914年)と同じ部屋に、河野通勢(こうの・みちせい)による《自画像》(n.d.)や、木村荘八(きむら・しょうはち)による《自画像》(1918年頃)が並べられている。
それらの並びからは、この時代の画家たちがいかに近い距離感で制作をし、現代からすると「パクリ」とも揶揄されてしまいそうなあり方で知や技術を共有し、その都度の表現形式を自由に選択しながら、「編集」的な手つきで作品を生み出していたことが分かる。
普通、展覧会の空間ではアーティストの独自性が強調されることの方が多い。しかし本展ではむしろ、劉生と後続の画家たちの編集的な手つきが強調されることによって、アーティストの「天才的」なイメージ(「アーティストは無から何かを創り出す」という幻想)に対する「編集」が試みられているようにも感じられた。
そうした「編集」的な試みは、画家・中原實(なかはら・みのる)の紹介においても見て取ることができた。
中原は、第一次大戦中にフランス陸軍の歯科医として従軍し、帰国後は前衛的な作品を発表したあと、関東大震災を経てオルタナティブ・スペースの画廊「九段」を開設し、前衛美術のオーガナイザーとしても活躍した人物である。
とはいえ、筆者は寡聞にしてこの画家の存在を知らなかった。おそらく一般的にも、この画家の存在はまだ広く知れ渡ってはいないのではないだろうか。
つまりここにも、作家自身が「編集」的な手つきで、その都度の表現形式を自由に選択しながら表現を行おうとする姿と、固定した歴史のイメージに対して「編集」的な手つきで介入を試みるキュレーターの仕事が垣間見られたのだった。


コレクション展「ただいま/はじめまして」
「ただいま/はじめまして」と題されたコレクション展は、修復を終えて展示室に復帰した宮島達男作品などによる「ただいま」と、休館中に新たにコレクションに加わった近年の作品による「はじめまして」が一堂に会する展覧会だった。
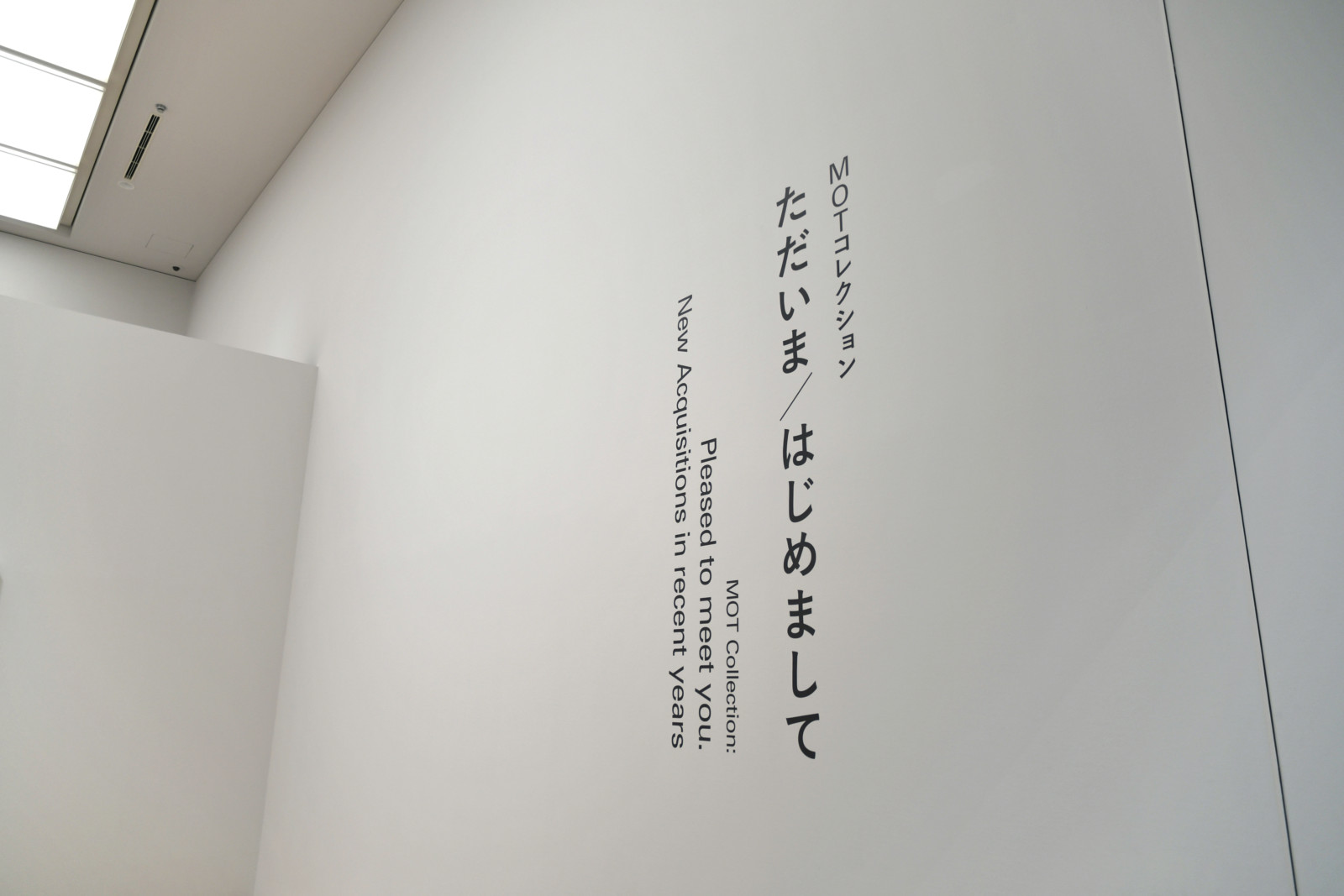

しかしこの展覧会では、学芸員の「編集」がいささか炎症を起こしているようにも感じられた。
「はじめまして」の部門で紹介されていた、主に1970年代生まれ(現在40歳前後)の画家たちによる抽象絵画──アメリカの戦後抽象絵画からの影響を強く感じさせるもの──の一群からは、現代作家の収集方針に対する偏りを感じざるをえなかったのだ。
そこでは、それぞれの作家の取り組みに対する個別の解説がなされたとしても、「編み手たち」において示されていたような、「なぜこの時代にこの作品なのか?」という「大きな問い」に対する答えが用意されていなかったのだ。その点において、「編集」という手つきの機能の仕方が企画展とコレクション展では対照的に働いていたようにも思われる。
そんなフジワラによる《毛皮たち》は、一瞥してオーソドックスな抽象絵画に見えるが、よく見てみると、それは動物の毛皮のコートの毛が刈られ、製造の際に付けられる印や傷が剥き出しになったアザラシの皮であることが分かる。

その点において、フジワラの「抽象絵画」は、先に述べた一連の抽象絵画とは対照的に、「なぜこの時代にこの作品なのか?」という大きな問いに対し、たった一点の作品で答えようと格闘する様が見られた。





